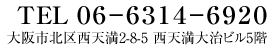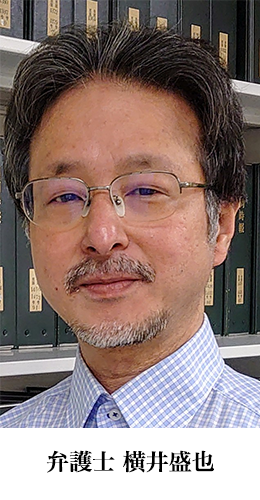 |
労役場留置という“懲役刑”
- 2012-07-20 (金)
- 横井弁護士
控訴審から弁護人を務めたある老女は、「何とか罰金刑ではなく懲役刑に変えてもらいたい。」と私に懇願しました。
一審判決は「被告人を罰金50万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
老女は、生活苦に喘いでいてお金もないし、体を壊しているので労役場留置には耐えられないというのです。
刑法9条に刑の種類が定められています。
「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」
そして、刑法10条1項に、「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」とあります。
つまり、刑務所に行くより罰金を払う方が刑は軽い。当たり前といえば当たり前のようなのですが、そうとも言い切れない場面に遭遇することがあるのです。
労役場留置とは、罰金を支払わない者を刑務所等に収容し、労役を課すというものです。
この老女の場合、1日5000円の換算とされましたので、一部でも罰金を支払えなかった場合には、(50万円÷5千円=)100日間、刑務所等で労役に服さなければなりません。
実務上、罰金刑に執行猶予が付されることはめったにありません。
一方、罰金刑より重い懲役刑の場合、初犯であれば執行猶予が付くことが往々にしてあります。
この場合、社会の中で執行猶予期間、罪を犯すことなく過ごせば、何らの刑を受けることもなくなります。
弁護人としては、被告人の罪を軽くする方向での弁護が求められるので、「罰金ではなく、執行猶予付きの懲役刑を」などという主張はできません。
この老女の場合、控訴審において病状が悪化していることや生活苦の状況を縷々立証し、「執行猶予付きの罰金刑を」とか「罰金の減額を」といった弁論を行いました。
控訴審の判決は、「原判決を破棄する。被告人を罰金40万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
罰金が10万円減額されただけでしたが、その後、検察庁との協議で毎月1万円ずつの分納ということで決着が付きました。
労役場留置が避けられない罰金刑は、執行猶予付きの懲役刑より過酷です。
実社会は、必ずしも法律の建前通りとはいかないようです。
(横井盛也)
- コメント (Close): 0
- トラックバック: 19
パチンコ依存症の社会問題
- 2012-07-18 (水)
- 横井弁護士
これまでに何件かパチンコに取り憑かれたことが原因で多重債務に陥った人の債務整理を受任したことがあります。
やればやるほど損をすることは頭の中ではわかっているのに、「少しでも取り返さなければ」とのめり込んでしまい、あげく依存状態から抜けられなくなってしまった、というのが共通パターンでした。
ホールに響く威勢のよい音楽、心地よい大当たりのアナウンス、出玉が溢れ出たときの震えるような快感。
現実社会の孤独や生活苦から解放されたその一瞬の再来を夢見て、なけなしの元手を手に、これまでの負けを少しでも取り戻そうとホールに通う。祈るような気持ちで、ハンドルを固定し、じっと座って台上を転がる玉を見つめ、時間を空費し、大金を浪費する。挙げ句、大きく人生を狂わされる、という具合です。
パチンコは、決して健全な娯楽でなく、悲劇的な結末に至る危険な賭博です。
近くで毎日営業しているのですから、アクセスの容易さは競馬や競輪の比ではありません。
そもそも金がないからパチンコで儲けようとして、さらに金がなくなるという悪循環。
消費税増税の際には必ずその逆進性が問題となりますが、パチンコの逆進性は消費税のそれどころではないはずです。
パチンコを全廃する必要がある――ずっとそんな思いを抱いていました。
先日、「パチンコに日本人は20年で540兆円を使った」(若宮健著・幻冬舎新書)を読んで溜飲が下がる思いがしました。著者の考えに全面的に賛成です。
韓国では全面禁止ができたのになぜ日本ではできないのか。パチンコ業界をめぐる政財官の癒着の構造、パチンコ番組やCMを垂れ流す堕落したマスコミの実態などパチンコの暗部を鋭くえぐった力作です。
「パチンコは世界一のカジノである。」
「パチンコ依存症はれっきとした病気である。」
「業界団体は警察の天下り指定席」
「日本には、パチンコの現実に向き合う真っ当な報道はないのか。」
「一般国民がパチンコを許容しているわけではない。」
「パチンコは全廃するしかない。」――。
多くの国民が考えていた正論を代弁してくれた書なのではないでしょうか。
できるだけ多くの人、特に政治家や警察官僚に読んでもらって、パチンコが賭博そのものであり、多くの国民の生活を破壊し、経済社会を歪めている実態を知ってもらいたいと思います。
また灼熱の夏がやってきました。
今年もまた、パチンコ店の駐車場で幼い命が消える悲劇が起きるのでしょうか。
(横井盛也)
- コメント (Close): 0
- トラックバック: 0
モンスターペイシェントと診療拒否
- 2012-07-17 (火)
- 横井弁護士
医療機関側の依頼による医事紛争案件を数多く扱っています。
大半は、患者に対して行った医療行為に過失があったのか否かといった案件ですが、中には明らかに患者側に問題があるケースもあります。
例えば、医師を大声で脅し必要のない睡眠薬を多量に処方させようとする、難癖をつけて診察室に居座り他の患者の診療を妨害する、スタッフや他の患者に対して暴言を浴びせたり暴力をふるったりして院内の静穏や秩序を乱すといったケースです。
医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」(応招義務)とあります。
そこでよく、「かくかくしかじか、このような患者でも診療を拒否できないのでしょうか。」といった相談を受けます。
医師法に応招義務違反についての罰則はありませんが、昭和30年の厚生省通達では、拒否できる正当事由が狭く解されており、場合によっては、医師としての品位を損する行為として行政処分を受けることもあるとされています。
とはいえ、医師の応招義務が正面から問題とされた裁判例はなく、医療環境が大きく変化した現在、正当事由の範囲は明らかではありません。
そもそも応招義務は、医師の職務には公共性があって、かつ業務を独占しているゆえ、急病人の放置は許されないという趣旨から定められたものです。
しかし、応招義務が必要とされた時代とは違って医師数は飛躍的に増加し、医療機関の機能分化や救急医療における地域連携も進んだ現代において、患者の重症度や特性、地域医療体制等を考慮せずすべての医師に一律応招義務を課すことに大きな疑問を感じます。
今ここで治療をしなければ健康被害を拡大させてしまうといった場面や他に治療をなしうる医療機関が近くにないといった場面で特段の理由もなく診療拒否したら、それはそれで問題ですが、その場合でも民法の不法行為責任を問えば済む話です。
医師法19条の応招義務規定は、もはや歴史的役割を終えたというべきではないでしょうか。
医療行為は医師と患者の信頼関係があって成り立つものです。
モンスターペイシェントの問題行動により信頼関係が破壊された場合において、診療に緊急性がなく、患者の医療的保護に問題が生じないときは、断固として診療を拒否できると考えるのが相当です。
モンスターペイシェントに振り回される必要はありません。ケースバイケースの判断になるでしょうが、犯罪行為があればすぐに警察を呼び、患者には他の病院や医院に行くよう申し付けたらよいと思います。
(横井盛也)
- コメント (Close): 0
- トラックバック: 1
日本固有の領土
- 2012-07-17 (火)
- 横井弁護士
東京都の石原慎太郎知事が進める尖閣諸島の購入計画に対し、心から賛同の意を表したいと思います。
日本固有の領土を守ることは国にとって最大の使命です。
本来ならば国が手を打たなければならないはずの問題であり、購入計画の発表は、無為無策の国に対し、目を覚まさせる一矢となったはずです。
石原知事の政治家としての力量に敬服するばかりです。
では、ロシアに占領されたままになっている北方領土は、どうすれば取り戻すことができるのでしょうか。
北方領土はもともとアイヌの生活圏であり、江戸時代に幕府(松前藩)の支配下に置かれました。
そして、幕府とロシア帝国との間で締結された日露和親条約において、両国の国境は、択捉島とウルップ島の中間線と定められました。
北方領土には色丹村、泊村など日本の地方自治体がれっきとして存在していたのであり、他国の領土となったことは一度もありません。
ところが、1945年8月9日、ポツダム宣言の受諾裁可の当日、ソ連は、日ソ不可侵条約を国際法に違反して一方的に破棄し、通告もなしに日本への侵攻を始めたのです。まさに火事場泥棒。許されない暴挙です。
国際法上、現在まで続いているロシアの実効支配が不法占拠であることは明白です。
北方領土が日本固有の領土であることに疑いの余地はありません。
先日、ロシアのメドベージェフ大統領が択捉、国後両島を訪問しました。
日本政府の記者会見は、不快の意の原稿の棒読み。おそらくロシア政府に対する抗議もあんなものなのでしょう。
失望です。
もっと他国のような強面外交ができないものかと思います。
本気で取り返すつもりであるなら、日本固有の領土なのですから、どんどん上陸して、敢えて国際問題を引き起こし、国際世論を喚起するという手もあると思うのですが…。
ちょっと過激すぎるでしょうか?
(横井盛也)
- コメント (Close): 0
- トラックバック: 0
団藤先生の訃報に接して
- 2012-07-02 (月)
- 横井弁護士
刑事法学者の第一人者で最高裁判事も務めた東大名誉教授の団藤重光先生が先月25日、98歳でお亡くなりになられました。
心よりご冥福をお祈りします。
死刑廃止論の理論的支柱、リベラル派の最高裁判事といった側面から新聞の一面に訃報が掲載されていましたが、法律を学んだ者は皆、また格別の感慨を抱くのではないでしょうか。
同じく東大名誉教授の平野龍一先生(1920~2004)とは刑事法学界を二分するライバルでした。
ある時期以降に刑法を学んだ者は「行為無価値論の団藤説」か「結果無価値論の平野説」のいずれかの選択を迫られ、その後の学説はすべてそのいずれかの系統を引き継いで発展していったといっても過言ではありません。
学界に及ぼした影響や功績は計り知れません。
刑法理論の観点から最も衝撃的だったのは、昭和57年7月16日の最高裁決定だろうと思います。
それまで共謀共同正犯否定説の旗手であった団藤判事は、詳細な意見を付けて肯定説に転じられたのです。
骨子、「社会事象の実態に即してみるときは、実務が共謀共同正犯の考え方に固執していることにも、すくなくとも一定の限度において、それなりの理由がある。」、
「法の根底にあって法を動かす力として働いている社会的因子は刑法の領域においても度外視することはできない」、
「共同正犯についての刑法60条は、改めて考えてみると、一定の限度において共謀共同正犯をみとめる解釈上の余地が十分にあるようにおもわれる」。
実際に実行行為を行わなくても背後で計画・指揮する黒幕を実行犯と同様に正犯として処罰することを可能にするのが共謀共同正犯肯定説ですが、実際の事件の処理に際して黒幕を正犯として処罰する必要性を感じられたのでしょう。
初めてこの判決を学んだ時には無節操な変節と感じたのですが、今では社会の実情に合わせるべく柔軟に学説を変えられたと評すべきであると考えています。
肯定説は当然のことのように実務に定着しました。
さらには、明示的な意思の連絡がない場合でも、黙示の意思の連絡が存在すれば、共謀者の地位や立場を踏まえた上で共謀共同正犯が認められる、とされるに至っています(スワット事件・最高裁平成15年5月1日決定)。
著書や判例でしか存じ上げない雲の上の学者ですが、その果たした功績や及ぼした影響力の大きさは多少なりとも理解しているつもりです。
合掌。
(横井盛也)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0