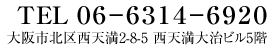- 2015-02-27 (金) 17:40
- 横井弁護士
生物学上の父子関係が認められないことがDNAによって科学的に明白であっても親子関係不存在確認の訴えによって父子関係の存否を争うことはできない。
最高裁第一小法廷平成26年7月17日判決(判時No2235)を読んで釈然としない思いを抱いています。
旭川家裁と大阪家裁で提起された2つの事件は一審、二審とも、嫡出でないことが科学的に明白であり嫡出の推定は働かないとして、子の夫に対する親子関係不存在確認の訴えを適法としていました。
民法では妻が婚姻中に懐胎、または婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻解消若しくは取消から300日以内に生まれた子は夫の子と推定され(民772条)、これを否定しようと思えば夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならないとされているのですが(民774~777)、旭川と大阪の一審、二審は、父子関係がないことがDNAで明らかなのだから嫡出推定は働かず、親子関係不存在確認の訴えが許されると判断していていました。
それを最高裁第一小法廷が3対2の僅差でひっくり返したのです。
2人の補足意見、2人の反対意見が付されていますが、4人とも立法政策の問題として検討がなされるべき旨を付言しています。
立法当時には想定されていない問題であり、法改正が追いつかない段階で判断を迫られた裁判官の苦渋が滲み出ています。
どちらの結論が正しいと言い切ることが難しい問題であることは間違いありません。
DNA検査など全く想定されていなかった時代においては、嫡出推定が父子関係を早期に安定させる上で大きな役割を果たしていたと思うのですが、科学的かつ客観的に父子関係がないことが明らかになる現代において、父子関係を推定することにどれほどの意味があるのか疑問を感じるところです。
旭川の事案では子の母とその夫がすでに離婚して親権者である母の下で暮らし、大阪の事案では子が母と生物学上の父と暮らしているとのことですから、嫡出推定が働かないという結論の方が具体的事案に即した妥当な解決が図れたような気がしてなりません。
この件については、大法廷回付されていませんから、判例変更はないという建前なのですが(裁判所法10条3号)、本当にそうなのでしょうか。
これまで最高裁は、離婚の届出に先立ち約2年ないし2年半前から事実上の離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合(最判昭44.5.29)、妻が懐胎した時期に夫が出征中であった場合(最判平10.8.31)に嫡出の推定が及ばないとしてきました。
にもかかわらず、嫡出でないことがDNA検査により科学的にほぼ100%否定されている今回のケースについて嫡出の推定が及ぶとすることは、明らかに矛盾しているように思います。
判例変更にあたるとして大法廷で審理すべき事案だったように思うのですが、みなさんはどう思われるでしょうか。
(横井盛也)
にほんブログ村
↑↑↑ ポチっ。↑↑↑